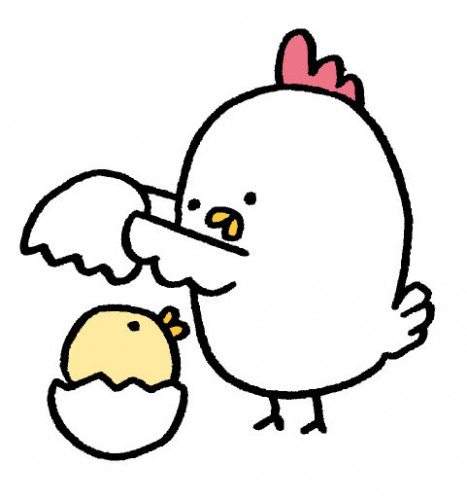母 ママ お母さん
近くのスーパーマーケットに立ち寄った時のこと。
レジで支払いを済ませようと並んでいると、お菓子コーナーから、
大きな声で泣き叫ぶ子どもの声が聞こえてきた。
見ると、3~4歳だろうか?
男の子が床に仰向けになって、買って買って~!!と暴れている。
傍には母親らしき女性が1人。
母親は、暴れる子どもを静かに眺めるように立っていて、時折、淡々と何やら子どもに言って聞かせているようだ。
多分、想像するに今は買わないよ、というようなことだと思う。
その親子は、ちょっとした有名人らしく、店員さん同士で「久しぶりだね~」などと囁きあう声が聞える。
私の番がきて、支払いを済ませようとすると目の前に、さっきの親子がいる。
帰る様子だが、子どもは諦めきれないのか、出口で床に寝そべり、またワーワーと大声で泣いている。
どうするのだろう?と興味の湧いた私が見ていると、
一時泣いて、ようやくあきらめがついたのか、その子は母親が「おいで」と広げた胸の中に、泣きじゃくりながら飛び込んでいった。
それを眺めていた私の胸に、こみあげてくるものがあった。
子どもが同じくらいの時、私は、スーパーに行くのが嫌だった。
必ずと言っていいほど、子どもは買って買って!とせがんでくる。
買わないことを伝えても一緒だ。
買って買って!!と諦めない。
そんな時、私は大体根負けして買っていた。
それは、泣かれるのが嫌だったから。
その様子を周りに見られて、うるさいな、と思われるのが嫌だったからだ。
「もう知らない!!」を決め台詞に、その場からさっさと離れたこともあったな。
あの時の私。
子どもに寄り添うことなく、周囲の目を気にして、とりあえず、その場をやり過ごすことの繰り返しだったと思う。
どんな風に接したらいいのか、わからなかったともいえる。
あの母親のように、子どもの気持ちを聴きながらも、できること、できないことを示す。
子どもの感情を無視することなく、怒りで押さえつけず、逃げもしない。
ジッと見守って、最後に受け入れる。
あの母親の姿に、私は神々しさを感じた。
親子を見ながら私は、母としての自分を映し出していたのと同時に、
子ども時代を重ねていたのだろう、あの子どもに羨ましさを感じたりもした。
当たり前のことだが、
子どもを産んだからと言って、今までと違う自分になれるわけではない。
子育てを通して、できれば知りたくなかった歓迎されない、自分の部分に気づかされる時があるだろう。
だから、苦しいと感じるお母さんも多いのではないか、と思う。
母親たるものこうでなければ、という思い、責任ともいえるもの。
一方、本当はこうしたい、という自分の思いだってある。
葛藤によって苦しみは起こる。どちらか片方だけならば苦しみは生まれないだろう。
苦しさは、自分の劣等感や罪悪感によって起こる。
子どもを持つ以前から、自分にあった未消化の部分だと思う。
母なら当たり前に、やること、こなすこと。
常識、当たり前、普通と言われること。
周りはできて私にはできない、という無意識的な思い込みがそこにないだろうか。
子どもの成長によって環境や対人関係は変わっていく。
色々な役割が思いのほか多すぎて、混乱状態になることもあるだろう。
適応できないと感じて、自分を恥じたり責めながらする孤独な子育ては、どれだけ辛いだろうと思う。
親だって苦手なことは沢山ある。
母たるものこうでなければ、から離れ、正直に飾らずパートナーや子どもに伝えてもいい。
色々な人がいるのだから、当たり前に色々な母親がいていいのだ。
お手本になるお母さんでなくても構わない。
え~!!って驚く位の個性的なママに魅力を感じることだってあるかもしれない。
あの、お母さんのようには、私は今もなれないだろう。笑
それでいい、それがいい。
完璧ではなく不完全なまま、そこそこのお母さんでいい。
子育ては、けして楽しいものでもない(笑)と安心して言い合えるような場が、もっと増えたらいい。
そして、1人でも多くの人を、巻きこみながらする子育てが、これからもっと広がるようなお手伝いができればと思う。
少数派?
私は、SNSが苦手だ。
特にグループチャットの類。
グループは友人、職場、母親同士と色々。
複数のメンバーで、リアルタイムに質問や返事ができるから、とても便利な反面、
私にとっては結構、困ることもある。
まず、誰に言っているのか?がわかりにくい。
そして、文字のやり取りが続くことで現れる、暗黙の了解みたいなものがわからず、
戸惑ってしまうことも多い。(-_-;)
相手の表情が見えない分、
文字から微妙な意味合いや、発信者の意図を想像してしまうことに疲れてしまう。
1対1ならまだしも、複数となると更に難しさは倍増する。
1番困るのは、
自分が、どのタイミングで返事をしたらよいかが、わからないこと(´;ω;`)
迷っているその間にも、次々と入るメッセージ。
ピンポーン!ピンポーン!と通知音の嵐!!
わ~~
どこで入ろう?と軽い焦りを感じたりもする。
ん??
入るタイミングを見計らうこの感じは、
小学生の時の大縄跳びに似てる!!笑
そんな些細なこと?に、不自由さを感じる自分に気づく。
こんな風なので、子育てでも色々、悩むことが多かった。
特に、親同士の関係については気苦労も多かった。
周りが、何気なくできることが私にはできない、という劣等感が自分を苦しめていたこともあったし、
親はこうあるべき、という思い込みの強さがあったのだと思う。
それが、不安や孤立感を作っていた。
他者との比較で生まれる苦しさは、
自分の中にある、沢山の自分を知るきっかけだ。
そこに丁寧に光を当てていくことで、
それぞれ持つエネルギーが方向づけられて、本来の力を取り戻していける。
自分を苦しめるものは、私の1部分であって、私の全てではないことに気づいていく過程。
どれもが生かされて調和することによって、
自分の中心に位置する、堂々として慈しみに満ちた尊い存在を知ることになるだろう。
今日は成人の日。
子どもにとっては、親の庇護から離れ、
1人前の成人として権利を得られると同時に、義務を果たす責任が生じる。
親にとっては、子どもの成長や発達を通して、
自分を見つめる日でもあると思う。
これからも、子どもであることには変わりはないけれど、
同じ時を生きる仲間として、私なりに見守り続けていくね。
こそだて
子育ては自分育て、と言われるけれど、
言い方を変えれば、
子どもを通して自分を知る、ことだと感じる。
知るとは、
自分に起こる感情や思いや記憶などに気づくことでもある。
子どもといて、どんな時に、どんな感情が湧いてくるのか?
それを、ジャッジしている自分はいないだろうか?
良い悪いは、他者との比較によって起こりやすい。
その他大勢の子どもの中で、違い、という形で現れるもの。
うちの子、よその子、から見えてくること。
幼少期の心身の発達や、皆と同じ行動ができないとか。
言葉を借りれば、発達障碍だとか、不登校だとか・・
一般的な状態でない?ことについて、親は心配になる。
この子に何が起こっているのか?
寄り添って何とかしてあげたいと思う反面、
どうして、この子はこうなのだろう?
と異質な者として見てしまう、そんな時もあるだろう。
私の育て方のせいなのか、環境のせいなのか・・・
頭の中で、ああだろうか?こうだろうか?と原因探しを始めてしまうことだってあるだろう。
それは、子どもと自分が一体化している状態ともいえる。
困っているのは一体誰なのか?
どんなことに困りごとを抱えているのか?
子どもに起こっていることと、自分に起こっていることを分けることが大切になる。
違和感、苦しさ、怒り、悲しみ
子どもを通して、自分に起こることに気づくこと。
それは、辛いものに触れることになるかもしれない。
私の中に、ずっとあった未解決なものに触れてくる体験かもしれないからだ。
それでも、1人ではわからなかったこと。気づかなかったこと。
それと少しづつ一緒にいられるようになれる時、
同じような仲間と共にいる場があることで
初めて、子どもに寄り添うことができるのだと思う。
子育てに、もともと成功も失敗もないはず。
「人を育てる」ことが、評価されてしまう世の中では安心は得られない。
親の孤立をますます仰いでしまうだろう。
自分を知るには、映し返すものが必要。
人が変化していくには、他者が必要なのだから。
自己の分身??
日々の生活を共にする者?
守るべき者?
愛する者?
私と子ども。
最も近い存在だけれど、私ではない者。
違うからこそ、理解したいと思う者。
相手を変えることなく、自分も刻まないで・・・
近ければ近いほど生まれてくる違和感。
それを丁寧に観ていくことで、次第に関係は変化していく。
悪い虫
日本では、乳幼児の夜泣きや、かんしゃくは、
体の中にいる「疳の虫」が、悪さをするからだ、という言い伝えがありました。
実際に、現在でも虫封じのおまじないや、祈祷をする、お寺や神社もあるようです。
あくまでも、困りごとの原因は「虫がいる」事であり、虫によって夜泣きや癇癪などの問題がおこっているという考えです。
だから、それを退治すれば問題は解決するということですね。
まさしく、これ、問題の外在化と言えるのではないでしょうか?
外在化とは、問題を当事者から切り離し、対象化して問題解決のためにアプローチする方法です。
簡単に言えば、その人自身と問題を切り離すということです。
何かが原因で、その行為が起こったということなので、
本人を否定することのない、優しい方法ともいえますよね。
また、何が問題なのか?が焦点化されるので、解決方法も見つけやすくなります。
私達、多くの人は、何かと自分をつなげて考えてしまうことがよくあります。
「○○で○○なダメな私」などです。
内面的な問題と、その問題が内在化されている状態です。
問題を問題としてとらえる事こそが問題で、本当は、人が問題ではなく、
問題となるものが問題だと気づくことができると、とても楽になれます。
また、焦点化されることで、具体的な解決方法がわかったりもします。
更に、問題と思われていたことは実は、問題ではなかった・・
という事に気づくこともあるかもしれません。
発達障碍を持つ子どもさんや、育てにくいと感じる、お子さんに対しても同じ事が言えると思います。
疳の虫のお話に戻ると、
成長していく過程で必要な虫であると知ることで、疳の虫を退治、することばかりでなく、
その虫と上手く付き合っていく術を身に着けることもできます。
子どものせいでもなく、親の育て方のせいでもない。
親自身が安心し、落ち着いて子育てに望むことが、子どもにも伝わり、
結果、安定していくという相乗効果を生み出すのです。
誰のせいにもしない、虫退治・・
実は深くて優しいセラピーともいえると感じます。